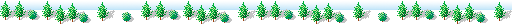
戞1復丂墱婼搟偐傜夛捗惣奨摴搾偺椃
戞1晹丂屼憼擖乮偍偔傜偄傝乯偺嫿
丂乽屼憼擖乿偲偼峕屗枊晎捈妽偺憼擖抧乮揤椞乯偺偙偲偱丄暉搰導偱偼撿夛捗孲慡堟偲戝徖孲偺戝敿丄偝傜偵撊栘導偺堦晹傪娷傓峀戝側抧堟傪偝偡丅孲嶳丄夛捗庒徏丄婌懡曽丄婼搟愳丄旜悾丒丒丒側偳偺庡梫側娤岝抧偲偼暿偵丄堦曕拞偵偼偄傞偲丄偦偙偵偼朙偐側嶳傗怷偑堢偰偨帬梴怺偄乽屼憼擖偺嫿乿偑峀偑傝丄娚傗偐側偲偒偑棳傟偰偄傞丅暯壐偲惷庘偲岾偣偺嫿丅椃恖偼嶳棦偺朙偐偝偲丄怱偺偸偔傕傝傪姶偠丄擔杮偺尨晽宨偵偙偙傠偍偒側偔傂偨傞偙偲偑偱偒偨丅
亙墱婼搟傊亜
丂帺戭傪6帪20暘偵弌敪偟偨偑丄僑乕儖僨儞媥壣偺拞擔偵摉偨傝丄僀儞僞乕僱僢僩偺摴楬忣曬偼乽5寧4擔丒搶杒帺摦幵摴壓傝偺廰懾偼憗挬偐傜巒傑傞乿偲寈崘偟偰偄偨丅
丂楙攏戝愹偐傜奜娐摴偵忔偭偰塝榓傑偱偼弴挷偵憱傞丅堦弖丄偙偺傑傑僗儉乕僗偵偄偗傞偺偱偼偲峫偊偨偑丄偝偡偑偵幵偺検偼懡偔丄愙怗帠屘傕偁偭偨傝偟偰廰懾傪梋媀側偔偝傟偨丅偦傟偱傕奣偹弴挷偵憱偭偰丄 8帪55暘偵惣撨恵栰僀儞僞乕偵摓拝丅
8帪55暘偵惣撨恵栰僀儞僞乕偵摓拝丅
丂椉懁偺杚応晽宨傪挱傔側偑傜丄憢傪奐偗丄偡偑偡偑偟偄嬻婥傪嫻偄偭傁偄媧偄崬傓丅嶳摴偵擖傝巒傔偨偲偙傠偺乽傕傒偠扟戝捿嫶乿偱媥宔丅廃埻偺嶳乆偼怴椢偵暍傢傟丄偦偺怴椢偼弔偺梲岝傪堦攖偵庴偗偰僉儔僉儔偲婸偔丅獯愳傪墎偒巭傔偨僟儉屛偼惷偐偵偨偨偢傫偱偄偨丅
亙僴儔僴儔亜
丂墫尨壏愹嫿偺擌傢偄傪捠傝夁偛偟偰奐柧嫶傪嵍愜丅崿傒偁偆擔岝廃曈傪旔偗丄杒偐傜夞傝崬傓儖乕僩偱墱婼搟壏愹嫿乽彈晇熀(傔偍偲傆偪乯壏愹乿偵岦偐偭偨丅 屲廫屲棦屛偺愭傪塃偵偲偭偰乽妺榁僩儞僱儖乿傪敳偗傞偲丄枮乆偲悈傪扻偊傞愳帯僟儉偵弌偨丅偙偙偐傜偼墱婼搟宬扟偺宬扟旤傪妝偟傒側偑傜偺僪儔僀僽偩偑丄摴偑嫹偄偨傔戝宆幵偲偺偡傟堘偄偵偼婋尟偑堦攖偱僴儔僴儔僪僉僪僉偱傕偁傞丅
屲廫屲棦屛偺愭傪塃偵偲偭偰乽妺榁僩儞僱儖乿傪敳偗傞偲丄枮乆偲悈傪扻偊傞愳帯僟儉偵弌偨丅偙偙偐傜偼墱婼搟宬扟偺宬扟旤傪妝偟傒側偑傜偺僪儔僀僽偩偑丄摴偑嫹偄偨傔戝宆幵偲偺偡傟堘偄偵偼婋尟偑堦攖偱僴儔僴儔僪僉僪僉偱傕偁傞丅
丂擔岝偺杒懁偵埵抲偡傞偙偺嶳怺偄壏愹偲宬扟偺嫿傊偼丄婥妝偵朘傟傞偲偄偆傢偗偵偼偄偐側偄丅搶嫗惣晹偺彫嬥堜偐傜幵偱擔婣傝偡傞偵偼彮偟墦偡偓傞偺偩丅弔廐偺娤岝僔乕僘儞偼廰懾傕憐憸傪挻偊傞丅偙偺擔偺傛偆偵帪娫傪婥偵偟側偄偱朘偹傞婡夛偼悢偊偰傒偰傕偦偆偁傞偙偲偱偼側偄丅
亙幹墹偺戧亜
丂搑拞丄乽幹墹偺戧乿傪尒傞偨傔偵丄宬扟偺嵶偄摴傪悢廫嘼壓傝壨尨偵壓傝偰傒偨丅墱婼搟偺惔棳偼戝彫偺娾傪愻偄側偑傜寖偟偔棳傟偰偄傞偑丄偙偺棳傟偼忋崅抧埐愳偺惔傜偐偝偵彑傞偲傕楎傜側偄丅娾娫傪丄悈偟傇偒傪偁偘偰棳傟棊偪傞愳偺懳娸偺拞暊偐傜丄幹墹偺戧 偑堦嬝偺巺偲側偭偰棊偪偰偄傞丅尒傞恖偲偰偩傟傕偄側偄丅偙偆偄偭偨岝宨偺廃埻偵偩傟傕偄側偄偲偄偆暤埻婥偑偡偽傜偟偄丅擔杮偺娤岝抧偼偳偙偵弌偐偗偰傕恖丄恖丄恖偱杽傑傝丄忋崅抧傪椺偵庢傟偽埐愳丒梀曕摴偼嬧嵗偺梉曽暲偺崿嶨傪掓偡傞丅怱傪惔傔傞偨傔偵偼悽懎偺墭傟偑偮偒偡偓偰偄傞丅偦偺揰丄柤慜傕抦傟偰偄側偄墱婼搟偺惔棳偵偼恖塭偡傜傒偊偢丄庘偲偟偰泲側傝丅
偑堦嬝偺巺偲側偭偰棊偪偰偄傞丅尒傞恖偲偰偩傟傕偄側偄丅偙偆偄偭偨岝宨偺廃埻偵偩傟傕偄側偄偲偄偆暤埻婥偑偡偽傜偟偄丅擔杮偺娤岝抧偼偳偙偵弌偐偗偰傕恖丄恖丄恖偱杽傑傝丄忋崅抧傪椺偵庢傟偽埐愳丒梀曕摴偼嬧嵗偺梉曽暲偺崿嶨傪掓偡傞丅怱傪惔傔傞偨傔偵偼悽懎偺墭傟偑偮偒偡偓偰偄傞丅偦偺揰丄柤慜傕抦傟偰偄側偄墱婼搟偺惔棳偵偼恖塭偡傜傒偊偢丄庘偲偟偰泲側傝丅
丂愳増偄偺幖抧偵丄敀偔壜楓偵嶇偔擇椫憪偺孮棊傪尒偮偗偨丅
丂墱怺偄嶳偺怴椢偲惔棳偱恎傪惔傔偰宬扟傪搊偭偨丅偙偙傑偱棃傟偽彈晇熀壏愹偼巜屇偺娫偩丅愳枔屛丄愳枔壏愹傪捠偭偰11帪50暘丄彈晇熀偵摓拝丅
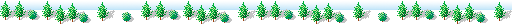
戞俀晹丂彈晇熀壏愹
丂弶傔偰朘傟偨偑丄乽娭搶偵巆偝傟偨桞堦偺旈搾乿偲偄傢傟傞嶳墱偺業揤晽楥偱偁傞丅
丂彈晇熀壏愹偼丄擔杮悘堦偺壏愹暚弌検乮枅暘1200儕僢僩儖乯傪屩傞傑偝偵壏愹揤崙丅儂僥儖偵晅懏偟偨業揤晽楥偵丄嬥愮墌側傝傪巟暐偊偽奜棃擖梺媞偼偩傟偱傕擖梺偱偒傞丅偨偩偟2帪娫丅宬棳傪朷傓峀乆偲偟偨掚墍晽楥偵偼暉傪屇傃晄榁挿庻傪摼傞偲揱偊傜傟傞幍暉恄偺搾傗丄摯孉晽楥側偳偑偁傝丄嬉戲側壏愹婥暘傪枮媔偱偒傞丅
亙丂揱丂愢丂亜
丂偙偙偵傕暯壠棊恖揱愢偑偁傝乽彈晇熀乿柦柤偺桼棃偲側偭偰偄傞丅
丂抎偺塝乮1185擭乯偱攋傟嶳墱傊偲摝偘偺傃偨側偐偵丄拞彨昉偲偄偆崅婱側昉偑偄偨丅昉偼曅帪傕朰傟傜傟側偄拞擺尵偑墱廈楬偵棊偪偨偲暦偒丄偦偺屻傪捛偆丅乮摉帪暯壠偺岞払偱拞擺尵偲偄偊偽丄惔惙偺嶰掜栧榚嵣憡丒嫵惙偺係巕丒拤夣偺傒偩偑丒丒丒乯
丂擇恖偼丄婼搟徖嶳傛傝尮傪敪偡傞婼搟愳傪偼偝傫偱丄抦傜偢塃娸偲嵍娸偵暿傟丄尩偟偄戝帺慠偺愻楃傪梺傃側偑傜屳偄傪扵偟偁偆丅偦傫側偁傞擔丄挿偄擭寧偺嬯楯偑曬傢傟偰丄婼搟愳傪夁偓崟戲偲杮棳偺崌棳抧揰乽嶰壒熀乿偺傎偲傝偱丄擇恖偼傔偱偨偔嵞夛傪壥偨偡偙偲偑偱偒偨丅偙傟偐傜屻丄乽嶰壒熀乿偼乽彈晇熀乿偲側傞丅敧昐桳梋擭偺嵨寧偑棳傟偨崱擔傕丄摉帪偲摨偠惔傜偐側悾壒偵棫偪徃傞搾崄偲嫟偵乽彈晇熀乿偺揱愢偼岅傝揱偊傜傟偰偄傞丅
亙丂柍丂忢丂亜
丂偦偺崟郪偐傜棳傟崬傫偩惔棳偑壏愹偺熀偺娾応傪丄壒傪棫偰偰棳傟偰偄傞丅備偭偨傝偲拫壓偑傝偺搾偵偮偐傝側偑傜棳傟壓傞悈傪挱傔偰偄傞偲丄偦偙偼偐偲側偔恖偺悽偺柍忢傪姶偠傞丅慜崁偵偟偐傝丄偍偛傞暯壠偼媣偟偐傜偢丅曐尦丒暯帯偺棎傪彑偪巆偭偨惔惙傕20擭偺塰壺偱偟偐側偔丄偦偺屻攅尃傪庤偵偟偨尮巵傕丄杒忦偵柦塣傪偮側偄偩傕偺偺棅挬埲崀偼傕傠偔傕曵傟嫀偭偨丅
丂壏愹偼嶳墱備偊偺偍偍傜偐偝偑枺椡偩偑丄偍偍傜偐偝傕夁偓傞偲尒嬯偟偔姶偠傞丅

亙偍偍傜偐側崿梺亜
丂偙偺壏愹偼愗傝棫偭偨奟忋偺峀偄娾掚偵12偺晽楥偑塃偲嵍偵暘偐傟偰揰嵼偡傞丅恀傫拞偵偺傒彈惈愱梡偺乽揤彈偺搾乿偲乽晍戃偺搾乿偑攝抲偝傟偰偄傞偑丄偦偺傎偐偼偡傋偰崿梺偲側偭偰偄傞丅応撪偼堏摦帺桼偩偐傜丄傇傜傇傜偲梙傜偟側偑傜愻柺僞僆儖堦枃偱慜傪塀偟偨抝惈偑彈搾偺廃傝傪減渏偡傞丅恖偺栚偑婥偵側傜側偄傎偳偺奐曻姶傪姶偠傞偲偼偄偆傕偺偺丄儖乕儖堘斀偺攜偺栚偼妉暔傪捛偭偰嵍塃偵摦偔丅
丂偦傟偱傕庒偄恖偨偪偼奣偹偍偍傜偐偱丄抝彈偺僌儖乕僾偼堦弿偵乽敀庻偺搾乿傗乽彫揤嬬偺搾乿乽曎嵿揤偺搾乿偵偮偐偭偰丄偼偟傖偄偱偄傞丅彈惈偼傕偪傠傫搾堖傪懱偵姫偒偮偗偰偄傞偑抝惈偼彫偝側僞僆儖堦枃偒傝丅儖乕儖偲偟偰偼僞僆儖傪梺憛偵擖傟偰偼側傜側偄丅帺怣偺偁傞側偟偑偙偙偱傕偺傪偄偆偐偳偆偐丒丒丒丅庒偄抝彈偺惗懺偵偮偄偰偼愱栧奜偱丄梋恖偵偼傢偐傜側偄悽奅偱偁傞丅
丂搾偼柍怓摟柧偱嵶偐側搾偺壴偑晜梀偟偰偄傞丅搾偵偮偐偭偰偼弌丄弌偰偼偮偐傞丅
丂惏揤偵宐傑傟壏愹梺偺傒側傜偢丄懢梲偺宐傒傪堦攖偵梺傃傞擔岝梺丄廃埻偺帺慠偑敪偡傞儅僀僫僗僀僆儞偺怷椦梺偲丄嶰梺傪妝偟傓偙偲偑偱偒偨丅1帪娫傎偳偺傫傃傝偟偨偁偲丄暪愝偺儗僗僩儔儞偱偦偽傪怘偟偨丅嶳嵷偺揤阯梾偑偟傖偒偭偲偁偘傜傟偰偄偰偍偄偟偐偭偨丅
亙怴椢偵堲傇亜
 丂堦晽楥梺傃丄偍暊傪枮懌偝偣傞偲柊婥偑廝偆偺偑忢偩偑丄婼搟愳偵増偭偰憱傞導摴乽愳枔壏愹愳帯慄乿偼嫹偄偆偊偵幍嬋偺僇乕僽偑楢懕偟丄楬柺傕偱偙傏偙偱偁傞丅偲偰傕壏愹偺梋塁偵傂偨偭偰偄傞偳偙傠偱偼側偄丅懱傪僴儞僪儖偺偆偊偵暍偄偐傇偝傞傛偆偵抲偄偰塃偵嵍偵僴儞僪儖傪愗傞丅栚偺偆偊偺偨傞傒偼偄偮偺娫偵偐徚偊偰偄偨丅
丂堦晽楥梺傃丄偍暊傪枮懌偝偣傞偲柊婥偑廝偆偺偑忢偩偑丄婼搟愳偵増偭偰憱傞導摴乽愳枔壏愹愳帯慄乿偼嫹偄偆偊偵幍嬋偺僇乕僽偑楢懕偟丄楬柺傕偱偙傏偙偱偁傞丅偲偰傕壏愹偺梋塁偵傂偨偭偰偄傞偳偙傠偱偼側偄丅懱傪僴儞僪儖偺偆偊偵暍偄偐傇偝傞傛偆偵抲偄偰塃偵嵍偵僴儞僪儖傪愗傞丅栚偺偆偊偺偨傞傒偼偄偮偺娫偵偐徚偊偰偄偨丅
丂愳枔丒愳帯偲壓傝丄愳帯僟儉傪嵍愜偟夛捗惣奨摴偵栠偭偨丅偙偙偐傜崱斢偺廻乽搾栰忋壏愹乿傑偱偼60km偺嫍棧偩丅
丂偄偮偺娫偵偐撊栘導偐傜暉搰導偵偼偄傝丄垻夑愳偑塃庤傪暯峴偟偰棳傟傞奨摴偼丄摴抂偺壴傕怓偯偄偰弴挷偱夣揔側僪儔僀僽偲側偭偨丅峠敀偺幣嶗偑愇奯傪揱偄丄儐僉儎僫僊偺弮敀偼椓偟偔丄儗儞僊儑僂傗嶳悂偺墿怓偑椢偺側偐偱嵺棫偭偰偄偨丅
丂扨慄偺栰娾揝摴乽夛捗婼搟愳慄乿偑夛捗傑偱暲傫偱憱偭偰偄傞丅撿夛捗孲揷搰挰傪宱偰丄壓嫿挰偵偼偄偭偨丅
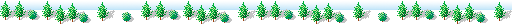
戞俁晹丂夛捗惣奨摴
亙搩偺傊偮傝亜
丂偙偺偁偨傝偱偼垻夑愳傪乽戝愳乿偲暿柤偱屇傫偱偄傞偑丄偦偺戝愳偑幹峴偟偰憱傞搾栰忋壏愹偺庤慜偵乽搩偺傊偮傝乿偲偄偆柤彑偑偁傞丅

丂昐枩擭傕偺挿偄擭寧偼丄嫮恱側娾偺怤怘偲晽壔傪孞傝曉偟丄妏偺庢傟偨娾偺摯孉傗撈摿偺崅偄娾搩傪憿傝弌偟丄偦傟偑怣嬄偺徾挜偲側偭偰偄傞丅僔儖僋儘乕僪偺僶乕儈儎儞傗塤浖偱尒傜傟傞杹奟暓偲偼堘偄揤慠偺娾偱偁傞丅乽傊偮傝乿偲偼丄乽嶳乿傪僇儞儉儕偵偟偰僣僋儕偼乽暏乿偲彂偔摿庩側暥帤偱丄偙偺抧曽偺曽尵偱乽愳偵増偭偨抐奟傗媫幬柺乿傪堄枴偡傞丅偙偺偙偲偽偼杒奀摴偱傕巊傢傟偰偄傞傛偆偩偐傜丄偁傞偄偼傾僀僰岅側偺偐傕偟傟側偄丅
丂岦偙偆娸偵傢偨傞栘偺捿傝嫶偑偐偗傜傟偰偄偰丄僊僔僊僔偲梙傟傞嫶傪嫲傞嫲傞傢偨傝丄奟熀偺摴傪墱偵恑傓丅戝愳偼偪傚偆偳僇乕僽傪昤偄偰偄偰丄悈偼怺偄偨傑傝偲側偭偰偄偨丅
亙丂婏丂娾丂亜
 丂偙偺乽傊偮傝乿偵楈尡偁傜偨偐側廫偺婏娾偑洣棫偟偰偄傞丅乽榟搩娾乿乽戦搩娾乿偵懕偄偰乽巶巕丒壆宍丒楨丒嬨椫丒旜宍丒徾丒岇杸丒捁塆朮巕乿偲柦柤偝傟偨崅偝10M傪墇偊傞搩娾偑戝愳増偄偵婥崅偔暲傫偱偄傞偺偱偁傞丅偦偺墱偵嫊嬻憸曥嶧偑釰傜傟偰偄傞丅
丂偙偺乽傊偮傝乿偵楈尡偁傜偨偐側廫偺婏娾偑洣棫偟偰偄傞丅乽榟搩娾乿乽戦搩娾乿偵懕偄偰乽巶巕丒壆宍丒楨丒嬨椫丒旜宍丒徾丒岇杸丒捁塆朮巕乿偲柦柤偝傟偨崅偝10M傪墇偊傞搩娾偑戝愳増偄偵婥崅偔暲傫偱偄傞偺偱偁傞丅偦偺墱偵嫊嬻憸曥嶧偑釰傜傟偰偄傞丅
丂乽嫊嬻憸曥嶧乿偲戣偟偨堦暥偑偐偗傜傟偰偄偨偺偱敳悎丅
嫊嬻憸曥嶧
梷乆摉強嫊嬻曥嶧僴丂墲愄戝摨擇擭丂嶁擵忋揷懞杹彨孯寶棫
抭宒偲暉摽偲傪庼偗媼偆丂杮摪偼曮楋嶰擭惓寧暅棫偣傝
丂歫屇
惔偄棳傟偼戝愳偺惞抧偵丂屆偄偲傕偑傜偲岎傢傝傪壏傔
懢屆偼嶳婥偵懪偪抌偊傜傟丂丂惵弔偺弮寜偵愻偄偡偡偑傟偰
鑹慠偲偟偰丂栚傪妎傑偡巚偄偩丂榁偄偨傞偼宧偆傋偔丂棅傓傋偔
庒偒偼垽偡傋偔丂梇乆偟偔檢乆偟偄丂偝傜偽夰偐偟偄桭傜傛
崌偊偽暿傟傞偺偼偙偺悽偺潀偩偑
丂丂偦傟備偊偵偙偦崱擔偺偙偺擔傪
婌傏偆丂愮枩偺巚偄傪偙傔偰丂埇庤偟傛偆丒丒丒丒丒 |
丂側偐側偐偺柤暥偱偁傞丅
丂偙偺曥嶧偺婅妡偗偼乽挿柦丂偍嬥帩偪丂墢寢傃乿偲偁偭偨偑傢偨偟偼壠懓埨擩傪婩婅偟偨丅抶偄屵屻丄撈摿偺宨娤傪掓偡傞恄惞側椞堟偱丄晄忩傪棊偲偟恎傪惔傔丄廻攽抧丒搾栰忋偵岦偐偭偨丅

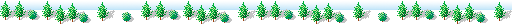
亙戝撪廻偼姙偺廻亜
 戝撪廻偼搾栰忋偐傜5亅6km嶳摴傪惣杒偵偼偄傞丅
戝撪廻偼搾栰忋偐傜5亅6km嶳摴傪惣杒偵偼偄傞丅
丂屵屻5帪傪夁偓偰偄偨偑偦偺擔偺偆偪偵偳偆偟偰傕尒偰偍偒偨偐偭偨偺偱丄栆僗僺乕僪偱摴傪媫偄偩丅
丂乽屼憼擖偺嫿乿偺側偐偱丄悢彮側偄峕屗帪戙偺巔傪巆偡奨乽戝撪廻乿丅
丂1590擭乮揤惓18擭乯4寧丄朙恇廏媑偼彫揷尨峌傔乮杒忦巵乯偱娭搶傪暯掕偟偨偦偺懌傪夛捗傑偱墑偽偟偨丅偦偺婣搑丄敀壨偵岦偐偆搑拞偙偺戝撪廻傪捠偭偨偲偄偆巎幚偑巆傞丅偟偐偟杮奿揑側敪揥偼峕屗弶婜偵夛捗斔弶戙斔庡丒曐壢巵偑夛捗偲擔岝丄峕屗偲傪寢傇惣奨摴偺嫆揰偲偟偰杮恮傪抸偄偨偙偲偵巒傑傞丅夛捗惣奨摴偼夢暷側偳偺暔帒偺桝憲偱塰偊丄夛捗斔庡傕嶲嬑岎戙偺嵺偵偼偙偺摴傪棙梡偡傞側偳廳梫側奨摴偱偁偭偨丅
亙峕屗偺椃恖亜
丂戝撪廻偺摿挜偼丄傢偢偐墱峴偒300m偺椉懁偺壠暲傒偵偁傞丅愥崙摿桳偺廳岤偱戝婯柾側婑搹憿丒姙晿偒壆崻偺柉壠栺係侽尙偑丄惍慠偲暲傫偱偄傞丅摴楬偼曑憰偝傟偰偄側偄偟丄揹拰傕抧壓偵杽傔傜傟偰偄傞丅偙偺宨娤偼傑偝偵峕屗帪戙偺傕偺丅
丂椉懁偺柉壠偼偦傟偧傟偑娤岝傪庡偲偟偨壠嬈偵惛傪弌偟偰偄傞丅乽柉廻乿乽柉寍昳揦乿乽偦偽偳偙傠乿乽偩傫偛傗乿乽夛捗幗婍偺揦乿乽傛傠偯傗乿側偳丄抧尦偺擾嶻暔傪偼偠傔偲偟偰丄愄夰偐偟偄嵶乆偲偟偨搚嶻昳傪丄尙傪暲傋偰斕攧偟偰偄傞丅5寧楢媥偺娤岝媞偼壠懓楢傟偑懡偔丄妝偟偦偆偵尙愭偵暲傇偦傟傜偺搚嶻昳傪慖暿偟偰偄傞丅

丂抧尦偺榁栮偵乽偙偺寶暔偼偄偮崰寶偰傜傟偨偺偱偡偐丠乿偲恥偹傞偲乽懡偔偼峕屗帪戙屻婜偐傜柧帯偵偐偗偰寶抸偝傟偨傕偺偱丄300擭偺楌巎傪帩偮傕偺傕偁傝傑偡傛丅乿 偲丂帺怣傪帩偭偨尵梩偑曉偭偰偒偨丅傢傟傢傟偑朘傟偨帪娫偼梉埮偑敆傞捈慜偱丄偡偱偵壠楬偵岦偐偆恖偨偪偑戝敿偩偭偨偑丄偦傟偱傕枹偩戝惃偑屆偄奨摴偺梋塁傪妝偟傫偱偍傝丄拫娫偺斏惙傪憐憸偡傞偲丄嶐崱偺娤岝僽乕儉偼偙偺嶳棦偵尷傝側偄壎宐傪梌偊偰偄傞傛偆偵傒偊偨丅
丂嵍塃偺懁峚偵惔棳偑怱抧傛偄壒傪棫偰丄惃偄傛偔棳傟偰偄傞丅堦暈偺惔椓嵻丅椻偨偄悈偼丄堸傒暔傗栰嵷椶傪椻傗偡栶妱傕壥偨偟偰偄偰丄棳傟偺拞偵娛價乕儖傗僕儏乕僗側偳偑偍偐傟丄奿埨偺抣抜偱娤岝媞偺偺偳傪弫偟偰偄偨丅儔儉僱丒僕儏乕僗奺100墌丄偲偙傠偰傫200墌丄抧價乕儖500墌栫丅
嵟墱偺崅傒偐傜梉宨偺廻応傪尒壓傠偟偨丅
丂梉擔偑搶懁偺姙晿偒壆崻傪徠傜偟丄奊傕偄傢傟偸岝宨偵曫慠偲棫偪恠偔偟偨丅峕屗偺椃恖偵側偭偨傢偨偟偑偄偨丅
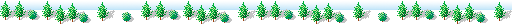
亙亙嬌忋偺搾亜亜
 丂屆偔偐傜朙晉側搾検乮尮愹偼俉儢強乯偲丄戝愳宬扟増偄偺梇戝側挱傔偱抦傜傟傞搾栰忋壏愹偼丄夛捗娤岝偺撿偺嫆揰偲偟偰搾廻偺揰嵼偡傞慺杙側壏愹奨丅旤敡傗旀楯夞暅偵敳孮偺岠擻偁傝丅戝愳偺壨尨偺側偐偵偼搾慏偩偗偺業揤晽楥傕偁傝椃忣傪偔偡偖傞丅
丂屆偔偐傜朙晉側搾検乮尮愹偼俉儢強乯偲丄戝愳宬扟増偄偺梇戝側挱傔偱抦傜傟傞搾栰忋壏愹偼丄夛捗娤岝偺撿偺嫆揰偲偟偰搾廻偺揰嵼偡傞慺杙側壏愹奨丅旤敡傗旀楯夞暅偵敳孮偺岠擻偁傝丅戝愳偺壨尨偺側偐偵偼搾慏偩偗偺業揤晽楥傕偁傝椃忣傪偔偡偖傞丅

丂崱彧偺搾廻偼奨摴嬝偺榁曑丒惔悈壆椃娰丅
偙偙偺業揤晽楥偼4偮偺堎側偭偨搾壏偺梺憛傪旛偊偰偄傞丅摓拝屻憗懍擖梺丅娐嫬傗愝旛偵偮偄偰偼昁偢偟傕報徾偺傛偄傕偺偱偼側偄丅夛捗揝摴偺揹幵偑椬傪憱偭偰偄偨傝丄僐儞僋儕偺懪偪偭傁側偟偺梺憛偼昳偵寚偗傞偑丄傂偲偨傃梺憛偵偮偐傟偽丄壏愹偼偦傫側偙偲傪姶偠偝偣側偄傎偳恎懱偵撻愼傓丅
亙丂曮丂庫丂亜
丂嵍庤偵曮庫傪帩偭偨棫憸偺丄偦偺曮庫偐傜搾偑棳傟擖傝丄偙傏傟偰偄傞丅偦偺憸偵偮偄偰丄偼偠傔弾柉媬嵪偺娤悽壒曥嶧偐偲巚偭偨偑丄巚偄側偍偟偨丅偙傟偼揤晹偺媑徦揤偩丅媑徦揤偼傎偲傫偳偑嵍偵曮庫傪帩偮丅僀儞僪偱媑徦偺堄偼岾暉丄拞悽埲崀擔杮偱偼暉恄偲偟偰偺怣嬄傪庴偗偰偄偨偑丄屻偵旤恖偺戙柤帉偲側偭偨丅偙傟偱側偧偼夝偗偨丅側傞傎偳惔悈壆偺搾偼旤恖偺搾偱偁偭偨丅
丂偟偐偟偙偺業揤偺晽楥偼晛抜偼崿梺偱丄彈惈偺擖梺帪娫偼屵屻7帪敿偐傜8帪敿傑偱偲寛傔傜傟偰偄傞丅僞僆儖椶傪搾偵擖傟傞偙偲偼偛朄搙偩偐傜丄堄傪寛偟偰僪儃儞偲偼偄傞偐丄寛傔傜傟偨帪娫偵偼偄傞偐擇偮偵堦偮偟偐側偄丅偙傟傎偳偝傛偆偵丄旤恖偲側傞偨傔偺嬯楯偼懡偄丅
 丂憗挬5帪敿偵姉抍傪敳偗弌偟丄挬搾偵偮偐偭偨丅愭媞偑偄偨丅朧傗偑晝恊偲偦偺桭恖偲偱搾偵偮偐偭偰偄偨丅乽楅栘偝傫偺偍偠偪傖傫両崱擔傕偲傑傞偺偱偡偐丠乿乽偁偁丄偲傑傞傛乿乽傢乕偄傢乕偄丄崱擔傕偲傑傞偺偱偡偭偰丅偄偄偹偄偄偹丅乿偲偼偟傖偄偱偄偨丅壠傪棧傟旕擔忢偺悽奅偵恎傪偍偔偙偲偼偩傟偵偱傕婌傃偱偁傞丅
丂憗挬5帪敿偵姉抍傪敳偗弌偟丄挬搾偵偮偐偭偨丅愭媞偑偄偨丅朧傗偑晝恊偲偦偺桭恖偲偱搾偵偮偐偭偰偄偨丅乽楅栘偝傫偺偍偠偪傖傫両崱擔傕偲傑傞偺偱偡偐丠乿乽偁偁丄偲傑傞傛乿乽傢乕偄傢乕偄丄崱擔傕偲傑傞偺偱偡偭偰丅偄偄偹偄偄偹丅乿偲偼偟傖偄偱偄偨丅壠傪棧傟旕擔忢偺悽奅偵恎傪偍偔偙偲偼偩傟偵偱傕婌傃偱偁傞丅
丂偺傫傃傝偲挬怘傪偍偄偟偔偄偨偩偄偰丄偙偺擔偺峴掱傪妋擣丅
亙塰屚惙悐亜
丂惔悈壆偼1990擭偵100廃擭傪寎偊偨偲偄偆偐傜柧帯23擭偺憂嬈丅嬼慠側偙偲偵傢偨偟傪堢偰偰偔傟偨婇嬈偲摨偠擭楊偱偁傞丅
丂偦傟傪婰擮偟偰丄乽壴捁壺傗偐晽寧偺廻乿偲戣偟偨崅媺儂僥儖乽摗棿娰乿傪怴愝偟偨丅暦偗偽丄嵟掅堦攽椏嬥2枩5愮墌偲偄偆丅僶僽儖偑壺傗偐側傝偟崰偱偁偭偨傠偆丅乽懅巕偑傗偭偰偄傑偡偑丄嬤崰偼宨婥偑偙傫側偱偟傚偆丒丒丒乿偲彈庡恖偼尵梩傪戺偟偨丅

丒丒丒丒傢偨偟傕偦偺偙傠偺偙偲傪巚偄弌偟偨丅婰擮帠嬈偲偟偰10壄墌偺梊嶼傪慻傒丄偦偺屻偺斏塰傪摢偵昤偄偰戝斦怳傞晳偄偵媦傫偩丅擔杮崙慡懱偵嬉戲偱壺旤側晽挭偑枲墑偟丄忔傝抶傟偨傕偺偼堄婥抧側偟偱偁傝楎摍惗偱偁傞偲峀尵偝傟偨丅偟偐偟偦傫側帪戙偼偄偮傑偱懕偔傋偔傕側偔丄柌偼偼偐側偔傕捵偊偨丅崱傕丄偦偺帪戙偵嶌偭偨僣働傪暐偆偺偵媯乆偲偟偰偄傞傕偺偑偄偐偵懡偄偙偲偐丅
丂偐偮偰壠峃偼嬉戲傪夲傔丄欏殽傪巪偲偟偨丅
丂岲傓偲岲傑偞傞偼屄恖偺彑庤偩偑丒丒丒偐傟偼偦偺巚憐偱俁侽侽擭偺婎慴傪嶌偭偨丅
亙懕偔亜
戞1復丂乥丂戞2復丂乥丂戞3復丂乥丂戞4復丂
仮丂椃俿俷俹
仮丂儂乕儉儁乕僕俿俷俹
Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved
![]()
 8帪55暘偵惣撨恵栰僀儞僞乕偵摓拝丅
8帪55暘偵惣撨恵栰僀儞僞乕偵摓拝丅 屲廫屲棦屛偺愭傪塃偵偲偭偰乽妺榁僩儞僱儖乿傪敳偗傞偲丄枮乆偲悈傪扻偊傞愳帯僟儉偵弌偨丅偙偙偐傜偼墱婼搟宬扟偺宬扟旤傪妝偟傒側偑傜偺僪儔僀僽偩偑丄摴偑嫹偄偨傔戝宆幵偲偺偡傟堘偄偵偼婋尟偑堦攖偱僴儔僴儔僪僉僪僉偱傕偁傞丅
屲廫屲棦屛偺愭傪塃偵偲偭偰乽妺榁僩儞僱儖乿傪敳偗傞偲丄枮乆偲悈傪扻偊傞愳帯僟儉偵弌偨丅偙偙偐傜偼墱婼搟宬扟偺宬扟旤傪妝偟傒側偑傜偺僪儔僀僽偩偑丄摴偑嫹偄偨傔戝宆幵偲偺偡傟堘偄偵偼婋尟偑堦攖偱僴儔僴儔僪僉僪僉偱傕偁傞丅 偑堦嬝偺巺偲側偭偰棊偪偰偄傞丅尒傞恖偲偰偩傟傕偄側偄丅偙偆偄偭偨岝宨偺廃埻偵偩傟傕偄側偄偲偄偆暤埻婥偑偡偽傜偟偄丅擔杮偺娤岝抧偼偳偙偵弌偐偗偰傕恖丄恖丄恖偱杽傑傝丄忋崅抧傪椺偵庢傟偽埐愳丒梀曕摴偼嬧嵗偺梉曽暲偺崿嶨傪掓偡傞丅怱傪惔傔傞偨傔偵偼悽懎偺墭傟偑偮偒偡偓偰偄傞丅偦偺揰丄柤慜傕抦傟偰偄側偄墱婼搟偺惔棳偵偼恖塭偡傜傒偊偢丄庘偲偟偰泲側傝丅
偑堦嬝偺巺偲側偭偰棊偪偰偄傞丅尒傞恖偲偰偩傟傕偄側偄丅偙偆偄偭偨岝宨偺廃埻偵偩傟傕偄側偄偲偄偆暤埻婥偑偡偽傜偟偄丅擔杮偺娤岝抧偼偳偙偵弌偐偗偰傕恖丄恖丄恖偱杽傑傝丄忋崅抧傪椺偵庢傟偽埐愳丒梀曕摴偼嬧嵗偺梉曽暲偺崿嶨傪掓偡傞丅怱傪惔傔傞偨傔偵偼悽懎偺墭傟偑偮偒偡偓偰偄傞丅偦偺揰丄柤慜傕抦傟偰偄側偄墱婼搟偺惔棳偵偼恖塭偡傜傒偊偢丄庘偲偟偰泲側傝丅
 丂堦晽楥梺傃丄偍暊傪枮懌偝偣傞偲柊婥偑廝偆偺偑忢偩偑丄婼搟愳偵増偭偰憱傞導摴乽愳枔壏愹愳帯慄乿偼嫹偄偆偊偵幍嬋偺僇乕僽偑楢懕偟丄楬柺傕偱偙傏偙偱偁傞丅偲偰傕壏愹偺梋塁偵傂偨偭偰偄傞偳偙傠偱偼側偄丅懱傪僴儞僪儖偺偆偊偵暍偄偐傇偝傞傛偆偵抲偄偰塃偵嵍偵僴儞僪儖傪愗傞丅栚偺偆偊偺偨傞傒偼偄偮偺娫偵偐徚偊偰偄偨丅
丂堦晽楥梺傃丄偍暊傪枮懌偝偣傞偲柊婥偑廝偆偺偑忢偩偑丄婼搟愳偵増偭偰憱傞導摴乽愳枔壏愹愳帯慄乿偼嫹偄偆偊偵幍嬋偺僇乕僽偑楢懕偟丄楬柺傕偱偙傏偙偱偁傞丅偲偰傕壏愹偺梋塁偵傂偨偭偰偄傞偳偙傠偱偼側偄丅懱傪僴儞僪儖偺偆偊偵暍偄偐傇偝傞傛偆偵抲偄偰塃偵嵍偵僴儞僪儖傪愗傞丅栚偺偆偊偺偨傞傒偼偄偮偺娫偵偐徚偊偰偄偨丅
 丂偙偺乽傊偮傝乿偵楈尡偁傜偨偐側廫偺婏娾偑洣棫偟偰偄傞丅乽榟搩娾乿乽戦搩娾乿偵懕偄偰乽巶巕丒壆宍丒楨丒嬨椫丒旜宍丒徾丒岇杸丒捁塆朮巕乿偲柦柤偝傟偨崅偝10M傪墇偊傞搩娾偑戝愳増偄偵婥崅偔暲傫偱偄傞偺偱偁傞丅偦偺墱偵嫊嬻憸曥嶧偑釰傜傟偰偄傞丅
丂偙偺乽傊偮傝乿偵楈尡偁傜偨偐側廫偺婏娾偑洣棫偟偰偄傞丅乽榟搩娾乿乽戦搩娾乿偵懕偄偰乽巶巕丒壆宍丒楨丒嬨椫丒旜宍丒徾丒岇杸丒捁塆朮巕乿偲柦柤偝傟偨崅偝10M傪墇偊傞搩娾偑戝愳増偄偵婥崅偔暲傫偱偄傞偺偱偁傞丅偦偺墱偵嫊嬻憸曥嶧偑釰傜傟偰偄傞丅
 戝撪廻偼搾栰忋偐傜5亅6km嶳摴傪惣杒偵偼偄傞丅
戝撪廻偼搾栰忋偐傜5亅6km嶳摴傪惣杒偵偼偄傞丅
 丂屆偔偐傜朙晉側搾検乮尮愹偼俉儢強乯偲丄戝愳宬扟増偄偺梇戝側挱傔偱抦傜傟傞搾栰忋壏愹偼丄夛捗娤岝偺撿偺嫆揰偲偟偰搾廻偺揰嵼偡傞慺杙側壏愹奨丅旤敡傗旀楯夞暅偵敳孮偺岠擻偁傝丅戝愳偺壨尨偺側偐偵偼搾慏偩偗偺業揤晽楥傕偁傝椃忣傪偔偡偖傞丅
丂屆偔偐傜朙晉側搾検乮尮愹偼俉儢強乯偲丄戝愳宬扟増偄偺梇戝側挱傔偱抦傜傟傞搾栰忋壏愹偼丄夛捗娤岝偺撿偺嫆揰偲偟偰搾廻偺揰嵼偡傞慺杙側壏愹奨丅旤敡傗旀楯夞暅偵敳孮偺岠擻偁傝丅戝愳偺壨尨偺側偐偵偼搾慏偩偗偺業揤晽楥傕偁傝椃忣傪偔偡偖傞丅
 丂憗挬5帪敿偵姉抍傪敳偗弌偟丄挬搾偵偮偐偭偨丅愭媞偑偄偨丅朧傗偑晝恊偲偦偺桭恖偲偱搾偵偮偐偭偰偄偨丅乽楅栘偝傫偺偍偠偪傖傫両崱擔傕偲傑傞偺偱偡偐丠乿乽偁偁丄偲傑傞傛乿乽傢乕偄傢乕偄丄崱擔傕偲傑傞偺偱偡偭偰丅偄偄偹偄偄偹丅乿偲偼偟傖偄偱偄偨丅壠傪棧傟旕擔忢偺悽奅偵恎傪偍偔偙偲偼偩傟偵偱傕婌傃偱偁傞丅
丂憗挬5帪敿偵姉抍傪敳偗弌偟丄挬搾偵偮偐偭偨丅愭媞偑偄偨丅朧傗偑晝恊偲偦偺桭恖偲偱搾偵偮偐偭偰偄偨丅乽楅栘偝傫偺偍偠偪傖傫両崱擔傕偲傑傞偺偱偡偐丠乿乽偁偁丄偲傑傞傛乿乽傢乕偄傢乕偄丄崱擔傕偲傑傞偺偱偡偭偰丅偄偄偹偄偄偹丅乿偲偼偟傖偄偱偄偨丅壠傪棧傟旕擔忢偺悽奅偵恎傪偍偔偙偲偼偩傟偵偱傕婌傃偱偁傞丅